デイサービス多様化の必要性
#介護
2021.04.12
みなさんが抱くデイサービスのイメージとはどんなものでしょうか?
厚生労働省が示すデイサービスの基本方針では
- 社会的孤立感の解消
- 心身の機能維持
- 利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減
3つがあげられています。
従来のデイサービスでは上記基本方針をもとに、体操や脳トレで心身機能の維持や向上を図ったり、様々なレクリエーションに参加してもらうことでスタッフや他の利用者とコミュニケーションをとり、孤立感を解消するなど、食事や入浴などの身体的な介助以外にも、とても重要な役割を果たしています。
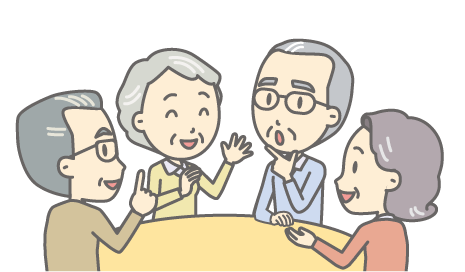
個人的な話になりますが、私の亡くなった祖母もデイサービスでのレクリエーションや昼食、お風呂に入れることなどをとても楽しみに通所をしていました。また、助け合い村の活動の中で接する方々からもデイサービスが楽しみという声は多く聞かれます。
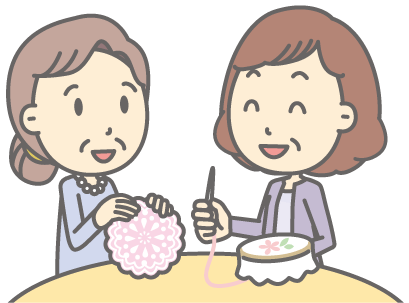
デイサービスのスタッフや他の利用者と会ってお話ができるのが楽しい、カラオケやレクなどをできるのが楽しいなど、楽しみにしている理由は人それぞれですが、大別するとコミュニケーションが取れる機会を楽しみにしているといった理由が多い印象です。
しかし、中には人とのコミュニケーションが苦手だという人もいて、レクレーションなどへの参加を苦痛に感じ、デイサービスに行きたくないという声を聞くこともあります。
規模の大小はあるにせよ、集団行動が基本のデイサービスでは、自分の意見が取り入れてもらえない、自由がないと感じ、やりたくもない体操やレクレーションなどをやらされていると感じてしまうようです。
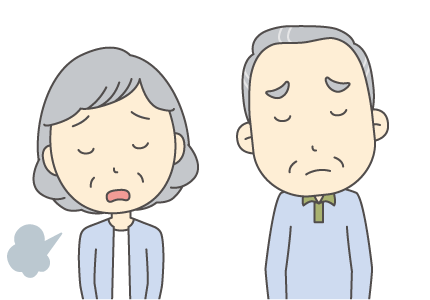
もともとデイサービスは、認知症医療の第一人者である長谷川和夫医師がその必要性を提唱し実現したものです。その後長谷川医師自身も認知症を患い、デイサービスに通所することになりましたが、提唱者である本人がデイサービスには行きたくないと家族に話をしています。
そのことに対して長谷川医師は、「なんでこんなことをしなくてはいけないのか。何がしたいですか?何がしたくないですか?そこから出発してもらいたい」と漏らしています。
提唱者の意見といえど、個人的なひとつの意見にすぎませんし、従来のデイサービスは必要不可欠なサービスであり、その在り方を否定するものでは決してありません。
しかし、こういった意見の人が一定数いることは確かで、デイサービスのさらなる多様化が必要になるのではと考えられるわけです。
デイサービスの利用者という集団の中には、認知症の人もいれば、身体的な理由で介助を必要とする人などいろいろな人がいるため、どこかに基準をあわせなくてはなりません。そこにはどうしても歪みが生じ、利用者によっては基準からの振れ幅が大きく、不満に感じる人が現れてきます。
不満を解消するには、利用対象者を絞り、基準からの振れ幅が小さいサービスの提供を行うことが求められます。
実際には、運営、人員、経営の問題などがあり、正に「言うは易し———」ですが、今後要介護者の数がさらに増加をしていくうえで、多様化を目指し選択肢を増やすことは、利用者の精神的な面からみても重要な課題であると考えられます。
