死因贈与契約のメリット
#相続遺言
2021.05.17
自分の死後、財産の行先をどのようにするかを考えた時
その希望を叶えるためには
文章や契約にして残す必要があります。
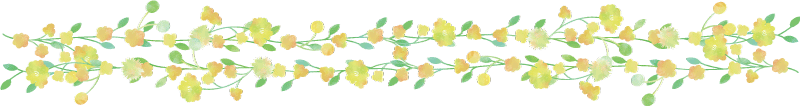
遺言書を作成し指定する方法が一般的ですが、死因贈与によってする方法もあります。
死因贈与とは、死亡を原因とする贈与のことで、贈与者と受贈者間で『契約を結ぶ』ことで財産の引き継ぎを行え、遺言と同じような使い方ができます。
死因贈与のメリット
(1)財産が行き場を失わない
遺言書の場合は、一方的な意思表示のため、もし受遺者に指定している人が財産を受け取らないといえば、その財産は行き場を失ってしまいます。(相続人がいる場合はそちらへ行きます)
対して、死因贈与の場合は、贈与者(与える側)と受贈者(もらう側)の双方の合意に基づく契約で行われるため、基本的に財産が行き場を失うことがありません。
また、遺言で行う遺贈とは異なり、贈与者(与える側)より先に受贈者(もらう側)がなくなった場合でも無効にはならず、その場合は受贈者の相続人に契約が引き継がれます。
(2)贈与者による一方的な撤回ができない
これは受贈者(もらう側)にとっては大きなメリットです。
例えば、AさんとBさんが、「自分(Aさん)がなくなるまで面倒を見てくれたら財産をすべてBさんにあげます」というような条件をつけた死因贈与契約を結びます。
10年間、Bさんは献身的にAさんの面倒をみていましたが、ささいなことからAさんの機嫌をそこねてしまい、Aさんは「Bには財産を一切あげない」と言い出しました。
もし遺言書でBさんに財産をあげると書いていた場合は、Aさんが遺言書を新しく書いてしまえばBさんは一切財産をもらえないことになります。
しかし、死因贈与契約の場合は、特段の事情がなければ一方的に撤回ができないため、Bさんが財産を一切受け取れないというはありません。
そのため、条件付きで財産を与えることを希望するならば、のちのトラブル回避のために死因贈与契約で行うといったことも検討するべきです。
(3)債務を負わない
遺言による受遺者の場合は、基本的に債務も引き継ぎますが、死因贈与の場合は、贈与者の債務は引き継ぎません。
贈与者がなくなった時点で、預貯金が2千万円、借金が1千万という場合でも、受贈者は2千万だけ受け取ることになります。
ただし、のちに債務者との間でトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
死因贈与契約書の作り方
死因贈与契約はワープロ打ちのような私文書でも有効ですが、のちにトラブルにならないように、
公正証書で作成することをおすすめします。
今回記述した内容は、一般的な考え方であり、異なった説や判例もあるため、契約にあたっては慎重に行う必要があります。
また、相続人がいる場合は、遺留分を請求される可能性があるなど、契約書を作成する際には、遺言書と同様に注意すべき点などを、専門家に相談をするほうがいいでしょう。
