認知症になった医師
#介護
2021.06.21
長谷川和夫医師をご存知でしょうか?
認知症診断に使われる、チェックシートがあります。日本では「長谷川式認知症スケール」が多く使われていますが、このチェックシートを考案したのが長谷川医師で、日本を代表する認知症専門医です。
長谷川医師は、今から数年ほど前に、自身が認知症を発症したことを公表しました。自身が認知症になった体験を、「日本人への遺書」として、「ボクはやっと認知症のことがわかった」というタイトルの本を出版しました。この本の「認知症になってわかったこと」という章の中で、認知症になった本人の実体験を書いていますので、その一部を紹介します。
認知症は固定したものではない
認知症の症状が出ているときと、普通の時とには連続性があります。朝がいちばん調子が良く午後1時を過ぎるとだんだん疲れて来て、何をしているのか分からなくなってきます。夜は疲れてはいるけれど、しなけらばならないことは決まっていることが多いので、なんとかこなせます。夜に眠って朝になるとまた頭がスッキリします。一度認知症になると固定した状態となるのではなく、調子の良い時があったりや悪い時があったりと変動するものなのです。
置いてきぼりにしないで
認知症と診断された人は「あちら側の人間」と思われています。あちら側とは、「まともに話ができない」とか「何を言っても分からない」とか思われています。
しかしそういうことはありません。
存在を無視されたり軽く扱われたりすると、苦痛や悲しみを覚えるものです。本人のことを何かを決める時、ボクたち抜きに物事を決めないで、置いてきぼりにしないでほしいと思います。
時間をかけて聴いて
認知症の人と接するときには、決めつけて話をしないでほしい。「こうしましょう」と決められてしまうと、混乱をしてしまい何も言えなくなってしまいます。認知症の人の話をよく聞くこと、時間がかかってでも何をいうのかを良く聴いてほしい。「今日は何をなさりたいですかと」と聞いてほしい。じっくり聴いてもらうことで安心します。あなたの時間を差し上げてください。
役割を奪わないで
認知症になったら「何も分からなくなる」ではありません。
心は生きています。
嬉しさや悲しさという感情はあります。認知症でも自分でできることはあります。生活をできるだけシンプルにして、見えやすく動きやすくすることが重要です。また、認知症の人を「支えられる側」の人として捉えるのではなく、その人の得意分野の役割を担ってもらう。うまくできたら褒めることも忘れずに。
複数のことを一度に言われてしまうと、混乱して疲れの度合いが深まります。
本にはこのように長川医師が認知症になって気づいたことが書かれています。
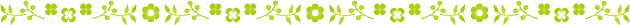
認知症になったからと言って
全く訳が分からなくなるわけではなく
違った人になるわけでもありません。
一人一人が違う存在であり一人一人が尊い存在であることを知り
その人を中心としたケアを行ってほしいと結ばれています。
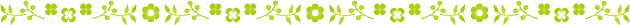
今後認知症の方と接する時の参考にしていただけたらと思います。
